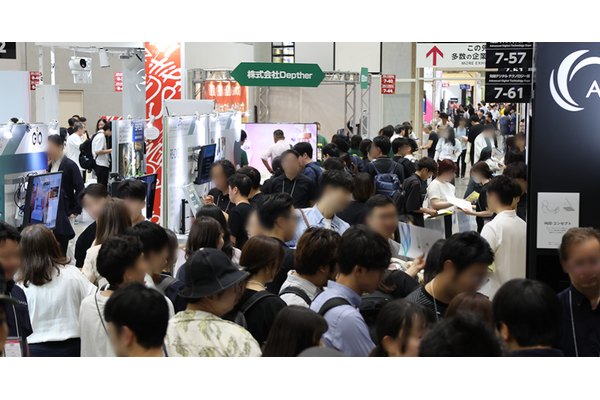2025年7月4日(金)にコンテンツ東京2025内で開催されたセミナー「コーポレート主語で届けるオウンドメディアのリアル~ファンの心の動き方を起点に~」では、サッポロビール株式会社 マーケティング本部 ビール&RTD事業部メディア統括 グループリーダーの杉浦若奈氏が登壇しました。記事サイト「CHEER UP!」や公式ファンコミュニティ「SAPPORO STAR COMPANY」、公式SNS等のオウンドメディアの運営を担当されている杉浦氏の講演のようすをお届けします。
コミュニティを「ファンと向き合う場」に変える
杉浦氏が現在の部署に着任したのは約3年前。当時はすでにファン向けのコミュニティが存在していたものの、中身はあまり進行できていない状態だったと語ります。運用資料を見返すと、そこには企業側からの一方的なメッセージが多く、「お客様とどう向き合うか」という視点が欠けていたことを感じたそうです。
また、運営するすべてのコンテンツの役割整理をしたときにコンテンツ同士が競合してしまうカニバリゼーションも起きていたとのこと。そうした課題を見つめ直し、目指したのは「企業視点」と「お客様視点」の両立です。分析だけにとどまらず、実際に参加・共創してくれるお客様の存在を重視し、「ロイヤリティ」を可視化する取り組みが始まりました。
心が動く行動トリガーを起点にした企画づくり
サッポロビールでは、従来の行動データや購買情報の分析だけでは捉えきれない「心の動き」に着目しました。企画の軸として独自に設定したのが、感情のスイッチとなる10個のトリガー(きっかけ)です。
1. キャンペーンに参加したい(インセンティブが欲しい)
2. ブランドを知りたい
3. ブランドに感情移入/共感したい
4. コーポレートを知りたい
5. コーポレートに感情移入/共感したい
6. イベントに参加したい
7. 誰かにおすすめしたい
8. ファン同士繋がりたい
9. サッポロビールと繋がりたい
10. サッポロビールで働いてみたい
これらは、お客様の感情のきっかけを「喜び」「驚き」「共感」など複数の要素に分類し、日常の中で感情がどのように動くか、企業はどう関われるのかという観点で設計されています。トリガーの設計には、会議室にこもって100個以上のお客様の行動や気持ちを出し合い検討を重ね10個に集約していったなど、深い思索があったと語ります。
その後、どのトリガーがお客様のロイヤリティ向上に貢献したのかを分析を進めたところ、トリガー 2:「ブランドを知りたい」トリガー 3:「ブランドに感情移入/共感したい」トリガー 7:「誰かにおすすめしたい」トリガー 8:「ファン同士繋がりたい」が効果的という結果でした。
最終的にこの4つのトリガーをフォーカスして企画開発を行っていくという方針になりました。商品を売るためのコンテンツではなく、お客様の心を起点に、どのようなきっかけを企業が創出できるかを考えることが重要だと杉浦氏は述べています。
事例紹介:内製イベントと共創プロジェクト
セミナー後半では、オウンドメディアの運用の流れでの社内社外を巻き込んだ取り組みに関して、事例紹介がありました。
【自社主導によるリアルイベント】
2024年8月に恵比寿ガーデンプレイスで実施されたリアルイベントでは、サッポロビールの社員が中心となって企画から運営までを担ったとのことです。「乾杯をもっとおいしく」をテーマに、事前に実施した調査で「乾杯に対するお客様のイメージ」を把握した上でコンテンツを設計しました。
当日は乾杯用のうちわ(ジョッキ風のデザイン)を作成するなど、非日常の楽しい体験を提供。イベント終了後には参加者・社員の両方からヒアリングを行い、得られた反応を次回以降の施策に活かしているようです。
【社外(代理店)との協働】
代理店との共同事例としては、大きく2つです。
1つ目は、ファンミーティングを実施しています。初回オリエンテーションはサッポロビールの社員が担当し、その後は代理店にご協力いただいているようです。オンラインでお客様と直接交流し、ブランド担当者が説明を行い、お客様の生の声を聞くことで、リアルな販促活動に繋げています。
2つ目は、お客様アンケートを軸としたものがあります。単にアンケートを取るだけでなく、ブランド担当者がお客様に伝えたいことや、お客様がアンケートで回答してくれることをきっかけに、企画全体を考えています。例えば、今年2月に缶で発売した「サッポロサワー 氷彩1984」は、今まで飲食店で愛飲されていた方の想いをマーケティング上で捉え、アンケートも募り、発売時の販促に活かしました。お客様の声を元にクリエイティブを制作し、公式SNSで発信することで、単なる募集で終わらせずファンの声をブランドに繋げるサイクルを回しています。
これらの取り組みで、お客様が喜んでいただけるポイントを把握し、しっかりとパターン化していくことも中長期的に運用していくという視点では重要だと考えているようです。
ファンとともに歩む企業・ブランドの未来
「私たちにとってファンはかけがえのない、なくてはならない存在であり、企業やブランドの未来はお客様とともに歩んでいくものだと考えています」と杉浦氏は語り、B to BやB to Cだけでなく、「B to F」(ファンの”F”)という考え方を推進して講演を締めくくりました。
サッポロビールのファンマーケティングは、「お客様の感情を起点に企業と共創する」設計思想に基づいています。商品開発、イベント、デジタル施策すべてにおいて、愛着を可視化しようとする姿勢は、ブランドの真のファンを育むための1つのモデルケースといえるのではないでしょうか。