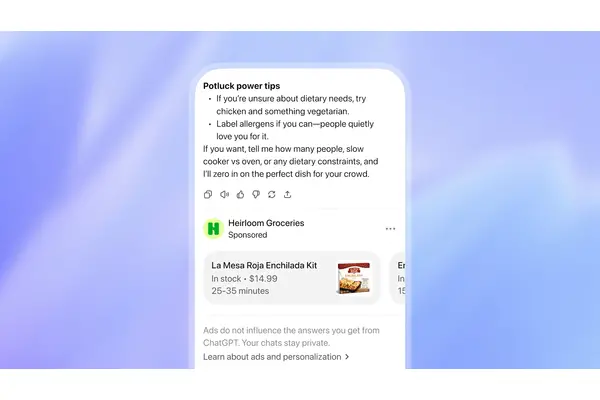Media Innovationが開催したカンファレンスイベント「Media Innovation Conference 2025」。同イベントより、キーノートセッション「日本にはコンテンツが足りない AIとメディアが築く幸せな関係」のレポートをお届けします。
セッションはTHE GUILD 代表取締役 / note CXOの深津貴之氏とストリーツ 代表取締役CEOの田島将太氏が登壇し、提示されたテーマを軸にAIとメディアが幸せな関係を築く方法についての知見を語り合いました。
普段どのようにAIを活用しているか
深津企画を形にするためのリサーチや情報分析、コンテンツの作成からレビューまで、さまざまな局面で活用しています。生成AIはネット上にある情報を平均的に学ぶので、平均的でさえあればみんなが満足してくれるもの、そうした部分はAIに任せます。逆に言えば、平均的なだけでは足りない箇所はAIには任せるべきではないということです。
田島私もリサーチで活用しています。また、今日のこの講演も話したいテーマをまとめたあと、AIに話の流れを考えさせました。自分の考えに足りない部分を補ってくれることもありますね。
ストレートニュースの価値はゼロになる
深津メディアのみなさんにお伝えしたいのは「ストレートニュースの価値は今後ゼロに近づく」ということです。もちろん、ニュースそのものの価値は変わりません。ニュースを“そのまま配信すること”の価値がなくなるということです。それを前提にコンテンツの編集や編成を再設計する必要があります。これまでは取材などで「第一報をすっぱ抜いて配信する」ことに意味があったかもしれませんが、AIが普及すると数秒、数分で追随されるようになり、アドバンテージがかぎりなく小さくなります。こうした構造の変化が、メディアビジネスにも影響を与えると予測しています。
田島他媒体と差別化を図るには「インターネット上にはない情報をいかに取ってくるか」という企画・取材の部分と、配信前にそれを人がきちんとレビューすること。つまり、入口と出口の重要性が増すのかなと。
深津そういう意味では、昭和時代の記者たちが重視したような「誰誰さんに取材したい?すぐにセッティングできるよ」と言えるようなウェットな能力が重視される時代が再来する可能性があります。そういう人がAIを活用するのが一番強い組み合わせです。

田島また、AIで情報を発信しやすく(記事を作成しやすく)なることで、団体や企業が自ら情報を発信するオウンドメディアが隆盛するかもしれません。ただ、メディアではない企業が良質なストーリーコンテンツをすぐに発信できるとはかぎりませんので、そこは大きなビジネスチャンスになりそうです。
AI活用を前提としたメディア体験はどのようなものになるか
深津「読者はホントに人間のままでいいのか」は考える必要があります。AIの活用で記事作成速度が上がると今よりもコンテンツがあふれかえるので、読者もAIで興味を持てそうなコンテンツを絞り込むようになる可能性があります。コンテンツを作るのも見るのもほとんどAIで、人間が見るのは上澄みの1%だけ。そんな世界がくる……とまでは断言できませんが、そうなってしまった場合に備える必要はあると思います。
田島もし本当にそんな日がきたら、AIのインターフェースもチャットではなくなりそうですね。
深津チャットは使い手からアプローチするインターフェースですからね。もしかしたら、AIの方からユーザーにアプローチする時代がくるかもしれません。たとえばGoogleカレンダーと同期してその人のアポイント予定を確認して「近日中に誰々さんと会うのなら、これとこれの話題は押さえておきましょう」と提案してくれるとか。
田島私はニュースを読むのが好きなので日頃からいろいろなサイトを見ています。しかし、世の中にはたくさんの情報があふれているというのに、上から下まですべて読みたい記事かというとそうではありません。そういう意味では、今はまだ「コンテンツの量が足りていない」状態なのかもと思うことがあります。
AIを追い風にできるメディアとは
深津自分たちが不得手な分野をAIに任せて、強みに全力でコミットする使い方をできるメディアが強いです。例えば調査報道が強みのメディアであれば、それ以外のことは極力AIに任せれば調査の時間をより多く捻出できます。
田島メディアの強みは、コンテンツメーカーがそろっていることも挙げられます。90点のコンテンツを100点に仕上げられる人はそうそういませんし、それはAIもうまくできません。だからこそ、そういう人を擁しているところは優位に立てます。

今日から生成AI活用を始めるにはあたってするべきことは
深津AIを「誰の(何の)ために」「どう使うのか」を最初に明確にしておきましょう。利益を上げるため、会社を生まれ変わらせるため、自分のスキルを上げるためなど、理由は何でも構いません。何をしたいのかを言語化しておかないと、することが小さくまとまりがちです。
田島ただ「とりあえず全社員がAIを使える環境を整えよう」では、社員はどう使えばよいか分かりませんし、上層部もどのようなAIを用意すればよいかを判断できません。最初にシミュレーションをしておけば、意思決定がスムーズになると思います。
会場で行われた質疑応答
最後に、会場でキーノートセッション終了後に実施された質疑応答の様子をお届けします。
―――AIで記事作成の速度が飛躍的に上がり、ストリートニュースの価値がゼロに近づいていくという話だが、AIによるニュースがファクトであるかどうかは誰がどのように担保するのか。
深津とても鋭い質問です。それは大きなビジネスチャンスだと考えています。たとえば。新聞社がAIの発信するニュースに対してファクトであるという保証の認定制度を展開したら、大きなお金が動くかもしれません。
―――もしメディアのAIがニュースを作り、読者のAIが記事を選定する未来がきたとき、メディアに望まれることは。
深津私見で言わせていただくと、一番重要なのは「信用と実績」です。言い換えるなら、いかにして「より本質的で、よりバリューのある記事を出し続けていると“AIに認識させるか”」が問われます。AIにそう思わせるには、今のSEOやSNSのテクニックは不要でしょうし、定期的に記事を発信していくのも大切でしょう。小手先の記事テクニックは通じなくなる時代がきそうです。
―――今、メディア企業がAIに対して取り組むべきことは。
深津AI対する解像度を上げておくことです。3年後や5年後の未来に向けて、スキルやアセットの整理を終えておきましょう。AIを触ったうえで「ウチはAIを使わずにがんばるぞ」と考えるなら、それはそれでいいと思います。ただ、AIをまったく触らない、使い方が分からないという状況はすぐにでもなくすべきです。
アーカイブ映像
Media Innovationの会員様向けにアーカイブ映像を用意しています。