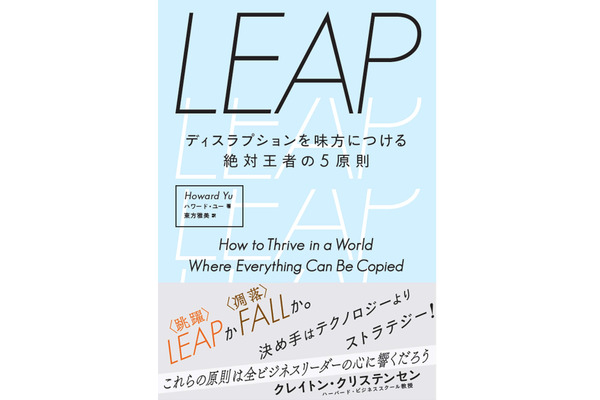1980年代から90年代にかけて、日本経済新聞をはじめとするメディア各社の戦略大転換をスリリングに描いたノンフィクション『勝負の分かれ目』が業界内外で話題を読んだ下山進氏の最新作。本書は、Yahoo! JAPAN、日本経済新聞そして読売新聞の3社を中心として、国内ニュースプラットフォームの覇権をかけた競争(と人間模様)を克明に綴ったノンフィクションとなっています。
2000年代半ばから2010年代後半にかけてのこの10数年、日本のニュースメディアはYahoo! を中心に回ってきたといっても過言ではありません。本書の序盤ではまず、Yahoo!がニュースコンテンツを核に国内最大のポータルへと飛躍を遂げていくさまが描かれています。すなわち、90年代末から00年代初頭にかけて、泥臭く粘り強い交渉の果てに主要な新聞社からの配信契約を取り付けつつ、情報料の支払いやリンクバックによるユーザー送客などの仕組みを作り上げていきます。なかでも、国内の購読数1位でピーク時には1000万部を超える部数を発行していた読売は、2001年にYahoo!から提示された破格の情報提供料と引き換えにニュース配信をスタート。Yahoo1の強力な集客コンテンツの一翼を担うことになります。
多くの新聞社がYahoo!になびく中にあって、そのプラットフォームに乗らないことを決断した日経は、2003年に就任した杉田亮毅社長の強力なリーダーシップのもとで、電子版の構築に邁進していきます。一方で、読売はビジネスのデジタルシフトという点では社内政治のゴタゴタが影響して遅れをとってしまいます。本書ではこうした新聞社・通信社とポータル(Yahoo!)との虚々実々(と言っても間違えではないでしょう)の駆け引きや人間模様を当事者への取材を通じて丁寧に描いています。
メディアのマネジメントやコンテンツ制作の現場の人間にとって、本書からどのような学びを得られるでしょうか。私からは大きく2点を挙げたいと思います。
目次
メディアが直面してきた「イノベーションのジレンマ」の克服に向けて
まずひとつは、「イノベーションのジレンマ」をいかに乗り切るかという点。「イノベーションのジレンマ」とは、経営学者のクレイトン・クリステンセンが提唱した用語で、既存のビジネスモデルが完成されているがゆえに、新しい市場への参入は既存収益が破壊されるリスクを懸念するあまり、乗り遅れてしまった結果、衰退を余儀なくされてしまうというものです。
とくに日本の新聞社の規模拡大は販売店による「拡張」(主としてさまざまなインセンティブを駆使した戸別訪問による売り込み行為)に負うところが大きかったという背景があります。部数の拡大は紙面広告の単価上昇によって新聞社本体を潤すだけでなく、折込チラシも増えることにつながり、これが販売店へのボーナスとなります。こうした拡張による部数の積み増しによって、さらなる拡張へと繋げるための原資が創出されるという“正のスパイラル”を生み、日本は“世界で最も新聞普及率が高い国のひとつ“に数えられるまでになりました。
しかし、たとえばサブスクリプションによる電子版への移行は、上で述べた販売店と新聞社の信頼関係とエコシステムを破壊するものとしてみなされてしまいます。サブスクの契約は原則クレジットカード支払いのため販売店にお金が落ちることがなく、スマートフォンやPCの画面で見る電子版ですから当然なから折込チラシの収入も入りません。電子版へ注力することは必然的に販売店と販売部(そして広告を取り仕切る営業)からの反発をも招くことになるため、読売・朝日含めた多くの新聞社は思い切った舵取りができませんでした。
唯一の例外として、いち早く電子版を立ち上げてサブスクビジネスに挑戦できた日経は、もともと宅配の比率が一般誌に比べて少なく販売店への依存度が小さかったことが成功の要因として挙げられます。
さらに、日経がいちはやくデジタルシフトに向けて一枚岩で取り組め(るように見え)た要因には、外的なビジネス環境が他社とは異なっていたからだけではありません。内部でも自らが「変わるべき」という雰囲気を醸成してきたからでした。
「日本経済新聞には、圓城寺次郎が始めた「長期経営計画」略して「長計」という素晴らしいシステムがあった。局を超えて優秀な若手、中堅が抜擢され、様々な課題について半年をかけて調査、経営陣に案を具申するというものだった。(中略)これは若手の頃から、目先の仕事だけに追われるだけでなく、長期的視野にたって自分たちの仕事がどうなっていくのかを考えることと同義だった」(1355-1358:数字はKindle版の位置番号。以下同じ)。そして2006年に他社に先駆けて専門部署である「デジタル編集本部」を立ち上げることで「会社は本気で電子新聞の有料化に取り組もうとしているらしい、というメッセージを発することになった」(1374)のです。
テクノロジーの普及により、情報を届ける手段が紙からPCへ、PC(ブラウザ)からスマートフォンやタブレット(アプリ)へと変わるタイミングでそれぞれのメジャープレイヤーが変わって来たように、これから先の同様のパラダイムシフトは起こるはずです。既存ビジネスを維持しながらも、シフトの予兆をつかみ取り「イノベーションのジレンマ」を乗り越えてユーザーを獲得するか。メディアはこの競争から逃れることはできません。
異なるカルチャーと利害を乗り越えた融合
さて、もうひとつの学びは、「メディア同士の協業のあり方」についてです。本書では、新聞社や通信社が連携してYahoo!からニュースプラットフォームとして対抗しようとする試みの顛末もいくつか描かれています。「あらたにす」「47News」がまさにそれですが、いずれもまだ続いてはいるものの、当初構想していた規模には遠く及んでいないというのが実情でしょう。こうした失敗(あるいは停滞)を見るにつけ、デジタルコンテンツ領域での新聞社間での連携は各社の利害関係がぶつかるだけでなく、紙の権益を守ることが前提になっているうえに、プロダクトアウト的な発想であり、読み手の側に立ったサービス設計ができないという事態に帰結します。
「実はウェブで成功するためには、いったん新聞記者であるという意識は捨てなければならなかった。しかし、この三社のサイト(筆者注:朝日・日経・読売の連携サイト「あらたにす」のこと)は、あくまで新聞記者の意識を前提に置きながら、それを世の中が読むべきだ、読むのが当然だという考えでつくったことが大きな失敗の原因となってくるのである」(2003)
加えて下山氏は「新聞社の技術力、企業風土では、プラットフォーマーに対抗するのはそもそも困難だったのかもしれない」(2132)とまで断じています。
協業の形は違えど2015年4月にローンチした「ノアドット」も同様のことが言えます。「ノアドット」は共同通信(及びその加盟社)とYahoo!JAPANが会社を作ってまで立ち上げたキュレーションサービスで、当事業を世に送り出した関係者らの情熱と努力の軌跡は本書でつぶさに描かれています。担当者が苦心して立ち上げたノアドットですが、キープレイヤーとして期待していた中日新聞はキュレーターとして参加を見送り、Yahoo!に至ってはキューレターにはならなかっただけでなく、ビジネス的な旨みがないと見るや出資比率を下げ関与を大きく減らしてしまうことになります。
「ヤフーとしては、現在のヤフー・ニュースが個別契約の好条件でまわっているかぎり、この超過利潤を手放すつもりはなかったのだ。ヤフーがキュレーターとして参加しなければ「ノアドット」自体のスケールは出てこない。(中略)このあと、ヤフーはノアドット事業への出資比率をどんどん下げていった」(4391-4406)。ここでも利害の衝突に起因する見込み違いが大きなつまずきとなってしまいました。
これは結果論ですが、上の事例を見る限りでは、対等の精神で協業したことで、自ずと合議制による意志決定の遅れを招いてしまうだけでなく、利益相反によりリスクを被る内部勢力に足を引っ張られてしまい、その取り組みは水疱に帰してしまうことになりました。もちろん、当事者はその場その場の判断で最善を尽くしたのであり、また別の取り組み方であれば成功できたとは断言できるものではありませんが、ひるがえって「私がもし当事者であったらどのような意志決定をするべきか」「現場でどう振る舞うべきか」を考える上で、重要な教訓になりうる事例として心に留めておくべきものと言えるでしょう。
著者の下山氏は「あとがき」のなかで、「未来を知るためには、まず歴史を知ること。そして歴史は誰かが粘り強く掘り起こし調査をしなければ、歴史にはならない」と記しています。まさにその意味で本書はメディアの未来を知るための一つの大きな手がかりになるはずです。