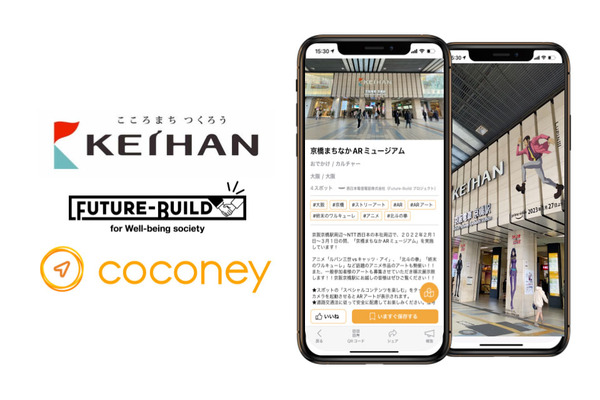ロイター研究所は、出来事やシチュエーションを一人称で体験できる没入型ジャーナリズムに関して、好例と呼べる5つの事例を紹介しました。VR(Virtual Reality)、AR(Augmented Reality)を活用したこの分野は、2015年から2016年にかけて盛り上がりましたが、ニュースルームへの導入は伸び悩んでいます。
著者は、没入型ジャーナリズムをニュースルームの持続可能な事業にする方法を探っており、紹介した事例からそのヒントを得たいねらいがあるようです。今回、BBC、El Paísなどの世界各地のメディアが実践した5つの事例を紹介していきます。
目次
ソーシャルメディア体験を模したニュースストーリー
ノルウェーの新聞社Verdens Gangは記事作成の方式について、編集者に大きな自由を与えています。その結果生まれたのがソーシャルメディア体験を模したニュースストーリー「Tinder Swindler」です。これはマッチングアプリTinderで若い女性を誘惑して大金を騙し取った男性についてのストーリーとなっており、スクロールするごとに動画や画像とともに語りかけが現れる全く新しい方式となっています。

この表現はTinderの使用体験に似た構成であり、まさにストーリーそのものを当事者視点で経験できる没入型ジャーナリズムと言えるでしょう。同社は、このフォーマット用の社内ツールを開発し、別の記事「Den digitale blotteren」も作成しました。こちらでは、未成年者に性的な画像を送りつけた犯罪者についての取材、被害者へのインタビューがSnapchatを模したフォーマットで展開されていきます。
これらの記事は、そのユニークさからニュースルーム内外で多くの評価を受けたといいます。