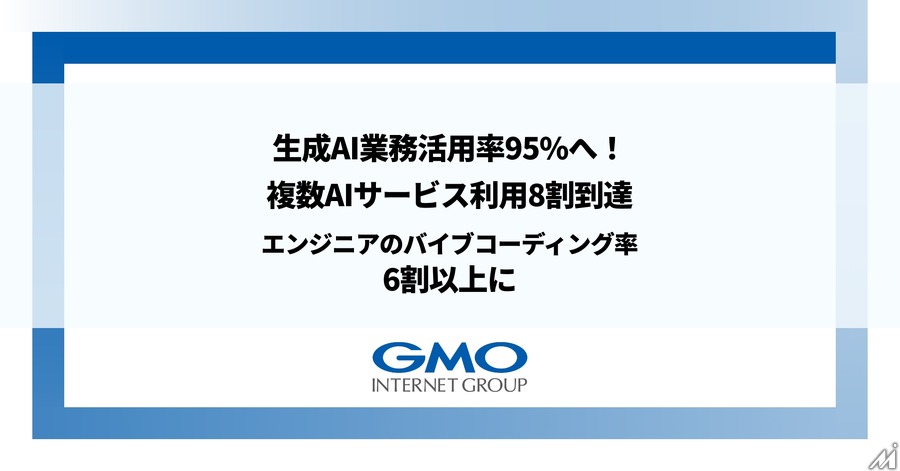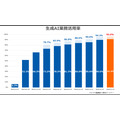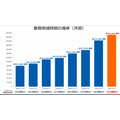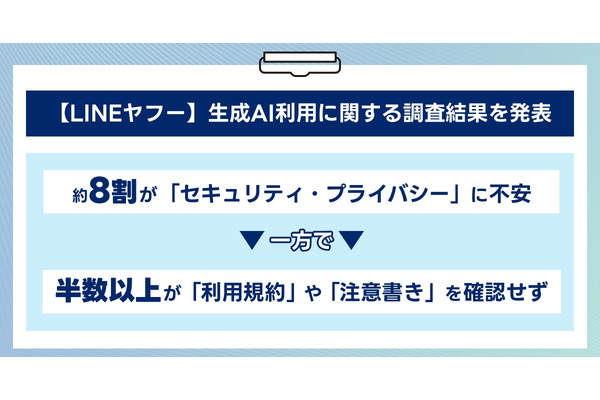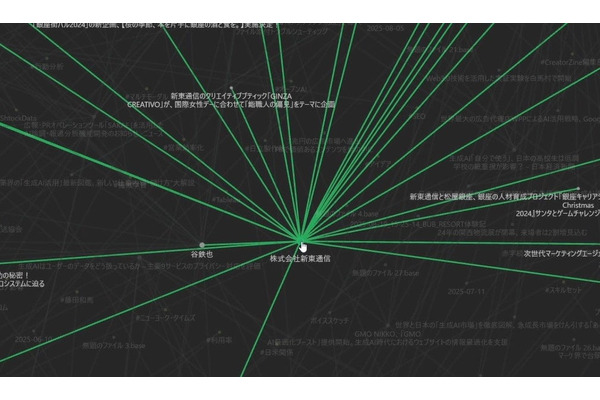GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷正寿)は、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全体で取り組む生成AIの活用・業務効率化の取り組みを進めています。四半期に一度実施している生成AIの活用に関する定点調査の最新結果を発表しました。
生成AI活用率が95.0%に到達、業務削減効果も拡大
2025年9月に実施した調査の結果、グループ全体の生成AI業務活用率は95.0%に到達しました。前回調査から0.9ポイントの増加となり、ほぼ全てのパートナー(従業員)が生成AIを業務に活用している状況です。
特筆すべきは、AI を活用しているパートナーの73.6%が「ほぼ毎日活用」しており、93.1%が「週1回以上」活用していることです。これは生成AIが日常業務に深く浸透していることを示しています。
月間の業務削減時間は約25.1万時間に到達し、前回調査から約2.7万時間の増加となりました。これは1,572人分の労働力をAI活用により得られている計算となり、同社の業務効率化への取り組みが着実に成果を上げていることが分かります。
複数AIサービス利用が1年で1.5倍に拡大
今回の調査で注目すべき点は、複数AIサービス利用率の大幅な増加です。生成AIを業務活用するパートナーのうち、複数AIサービス利用率は80.0%となり、前回調査から12.3ポイント増加しました。
2024年9月の調査では54.2%であったため、1年間で約1.5倍に増加したことになります。これは各AIサービスの特性を理解し、用途に応じて使い分ける高度な活用が進んでいることを示しています。
「GMO AIブースト支援金」が有料サービス契約を後押し
有料サービスの契約率は73.5%となり、前回調査から28.0ポイントの大幅増加を記録しました。これは今年6月より開始した「GMO AIブースト支援金」の効果によるものと考えられます。
同社は、生成AIはサービスやモデルごとにできることや得意なことが異なるため、これらを用途により使い分けることで、さらに精度の高い生産性向上が見込めると考えています。複数の生成AIモデルを比較できるサービスとして「天秤AI byGMO」を提供しており、本サービスの活用を社内でも推奨しています。
エンジニアのバイブコーディング実践率は6割超え
RPAやExcelなどでの業務スクリプトの自動化や関数生成、さらにエンジニアによるGitHub Copilotなどの IDE支援ツール活用といった「生成AIコーディング率」は、エンジニアでは88.0%、非エンジニアでも46.3%となりました。
Gemini CLIやClaude Codeといった「AIコーディングエージェント」を利用したバイブコーディングを業務で実践しているエンジニアは30.2%にとどまりましたが、既に試しているエンジニアも30.2%で、合計60.4%が経験済みでした。
バイブコーディングはセキュリティや品質担保といった点でまだ課題もあり、今後業務へどのように導入するかを模索・検討している段階であると推察されます。
AI活用の「質」を重視する段階へ
調査結果からは、AIに任せる業務と人間が担当すべき業務の役割分担が明確になってきていることが読み取れます。どのような業務でも、最終調整・意思決定をするのは人間がやった方がいいという回答が多く見られました。
直近ではAIの失敗するパターンが分かってきており、AIは「たたき台・変換・要約・アイデア出し」といった業務を任せるのが良いといった意見がありました。
1年前の調査では「コード生成は人間がやったほうが良い」という回答が多く見られましたが、現在はバイブコーディングの活用が浸透してきています。1年でAIに任せられることと、人間がやったほうが良いことの内容に大きく変化が出てきたことが分かりました。
パートナーが考える「AI活用上手」の条件
調査では、パートナーが考える「生成AIを使いこなせている人」の特徴についても聞きました。多くの回答で共通していたのは、AIサービスやモデルごとの特性を理解し、適切に使い分けられる人という点でした。
「AIサービスやモデルごとの特性、そのサービスの学習モデルや仕組みを理解し適切に使い分けたり、適切なプロンプトを投げたり適切な用途に自然に使えたり、学習モデルごとのバックボーンやメリット・デメリットを比較検討し取捨選択できる人です」といったコメントが寄せられました。
以前までは、とにかくさまざまな業務で生成AIを活用する「量」の部分が重視されていましたが、直近では生成AIの活用法を理解し適切な業務に利用する「質」の部分を追求できる人が使いこなせる人の条件であると推察されます。
同社グループ内AI推進プロジェクト「AIしあおうぜ!」リーダーの李奨培氏は、今回の調査結果について「生成AIの活用が量から質へと変化している段階にある」とコメントしています。
GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスを提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。グループ110社以上に在籍する約8,000名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者(エンジニア・クリエイター)が50%を超えています。