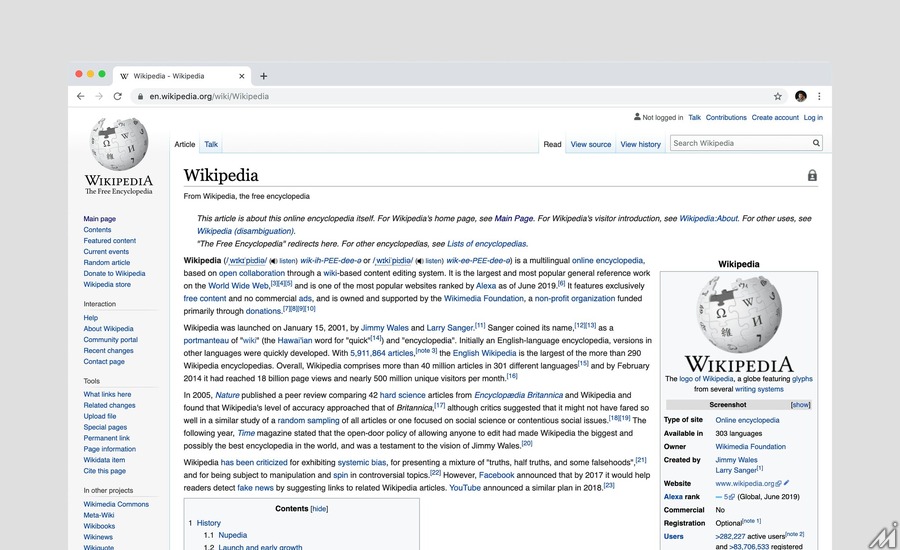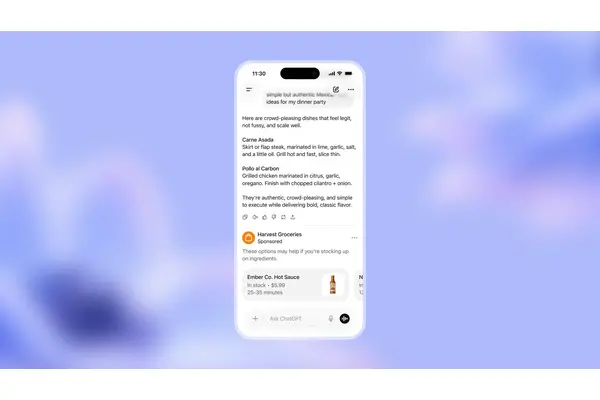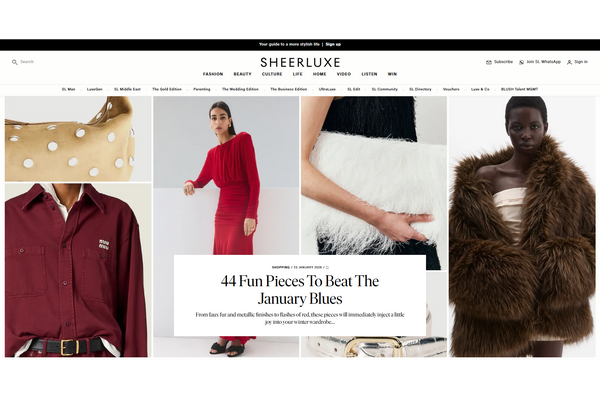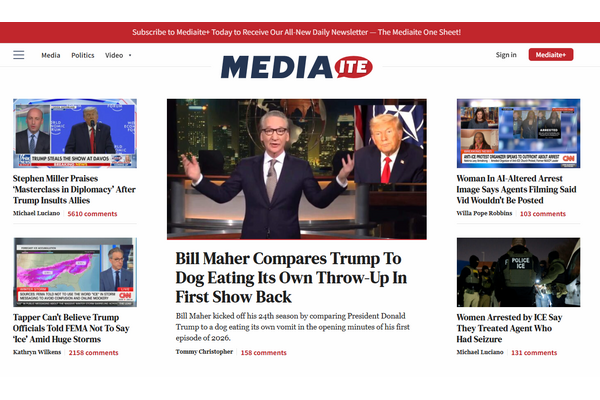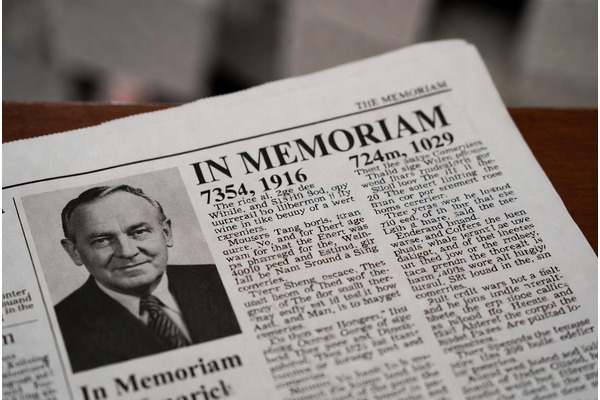おはようございます。Media Innovationの土本です。今週の「Media Innovation Newsletter」をお届けします。
メディアの未来を一緒に考えるMedia Innovation Guildの会員向けのニュースレター「Media Innovation Newsletter」 では毎週、ここでしか読めないメディア業界の注目トピックスの解説や、人気記事を紹介していきます。ウェブでの閲覧やバックナンバーはこちらから。
会員限定のコミュニティ「イノベーターズギルド」を開設しました。Discordにて運営しています、こちらからご参加ください。
★アプリも提供中です → AppStore / Google Play
今週のテーマ解説 知識インフラとして不可欠な存在に君臨も、多方面から攻撃を受けるWikipedia
以前は信頼のおけない情報源の代名詞だったWikipediaですが、いつの間にかプラットフォームやAIも依存する、デジタル上の知識のインフラとしての地位を確立しました。1日7000万人が利用し、広告収入に頼らず、年間1億7000万ドルの寄付で成り立っています。
Wikiedpaiはジミー・ウェールズ氏が1999年に無料のオンライン百科事典を作ろうと立ち上げたのがスタートです。もともとNupediaという編集者による百科事典を作ろうとしましたが、記事がなかなか集まらず、wiki形式にして一般のユーザーによる執筆を募ったところ急成長。多数のユーザーが参加するためのルール確立の過程で「中立的観点(NPOV)」という編集基準であり、協力のための「社会的概念」が生み出されました。
そんなWikipediaについて、The Vergeが「Wikipedia is resilient because it is boring」(Wikipediaは退屈だから強靭だ)という長文の特集記事を掲載していました。「中立的観点」を貫き、劇的な真実追求ではなく、ウェールズ氏の「何が真実かではなく、人々が何を信じているかについて書く」という姿勢を貫くWikiepdaiの現状と課題についてまとめてみます。