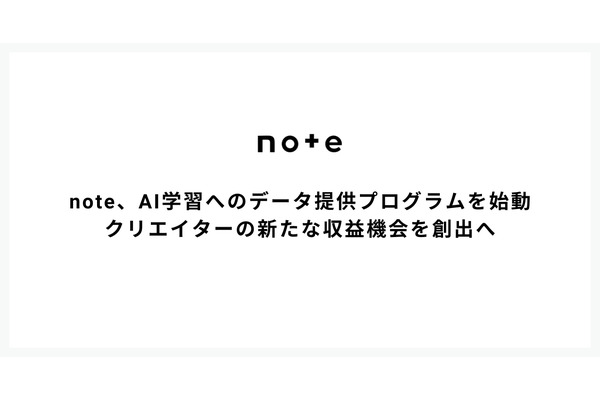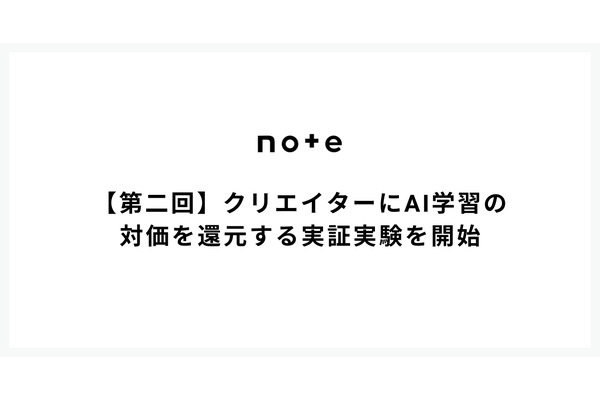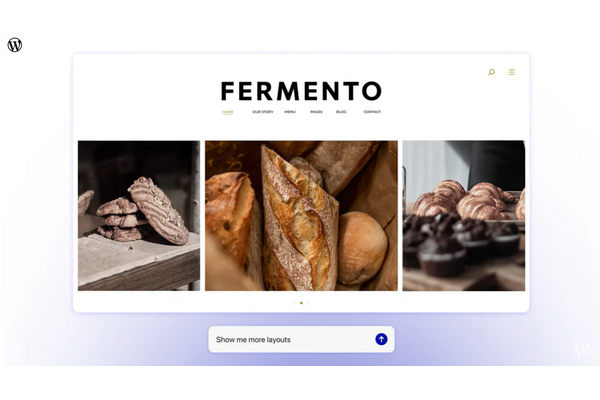Media Innovationの2022年8月企画は「メディアを支える大黒柱、進化するCMSについて考える」と題して、メディアを運営するためのプラットフォームであるCMSについて取り上げます。
note株式会社は「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。」をミッションとして掲げ、クリエイターが文章やマンガ、写真、音声などを投稿できるメディアプラットフォーム「note」を提供しています。
登録しているクリエイターは500万人を突破(2022年4月)。誰でも簡単に自分のコンテンツを販売できる仕組みがあり、10万人を超えるクリエイターが収入を得ていて、年間のトップ1000クリエイターの平均で667万円も稼ぐという場に成長しています。まさに情報発信の民主化、クリエイターエコノミーを体現するプラットフォームです。