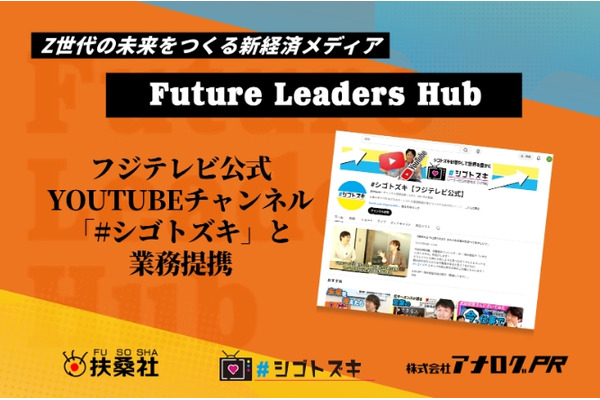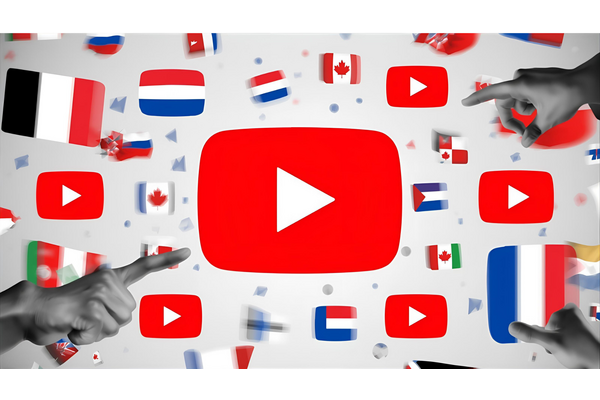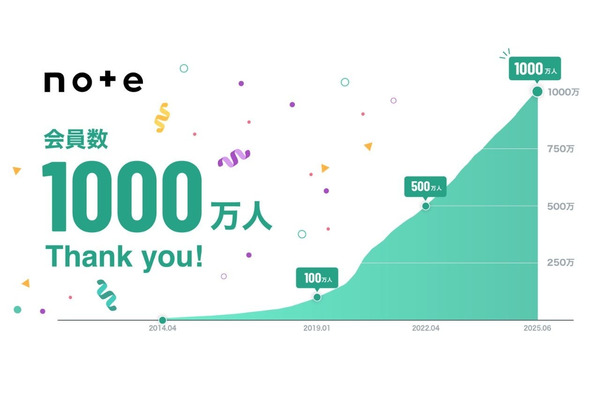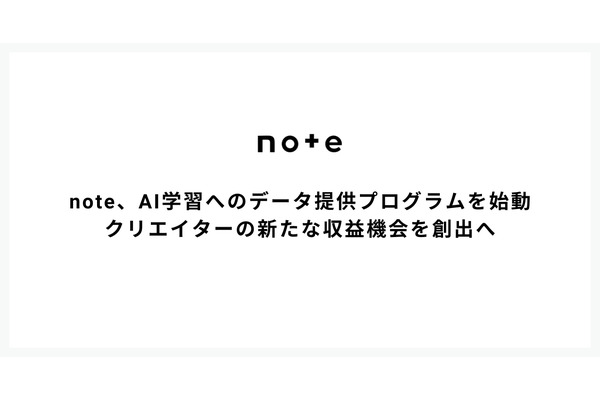YouTubeが、クリエイターの収益化に関するポリシーを見直すことを発表しました。7月15日に実施される今回のポリシー更新は、「非本物」コンテンツの収益化を制限することを目的としており、AI技術の普及によって急増している大量生産型コンテンツへの対策として注目を集めています。
YouTubeパートナープログラム(YPP)では従来から、収益化の条件として「オリジナル」かつ「本物」のコンテンツのアップロードを求めてきました。しかし今回の更新では、現代における「非本物」コンテンツの定義をより明確化し、大量生産型や反復的なコンテンツをより効果的に識別できるガイドラインが導入されます。
この政策変更の背景には、生成AI技術の急速な普及があります。テキストから動画を生成するAIツールの登場により、AI音声を写真や動画クリップに重ねた低品質なコンテンツが氾濫している現状があります。